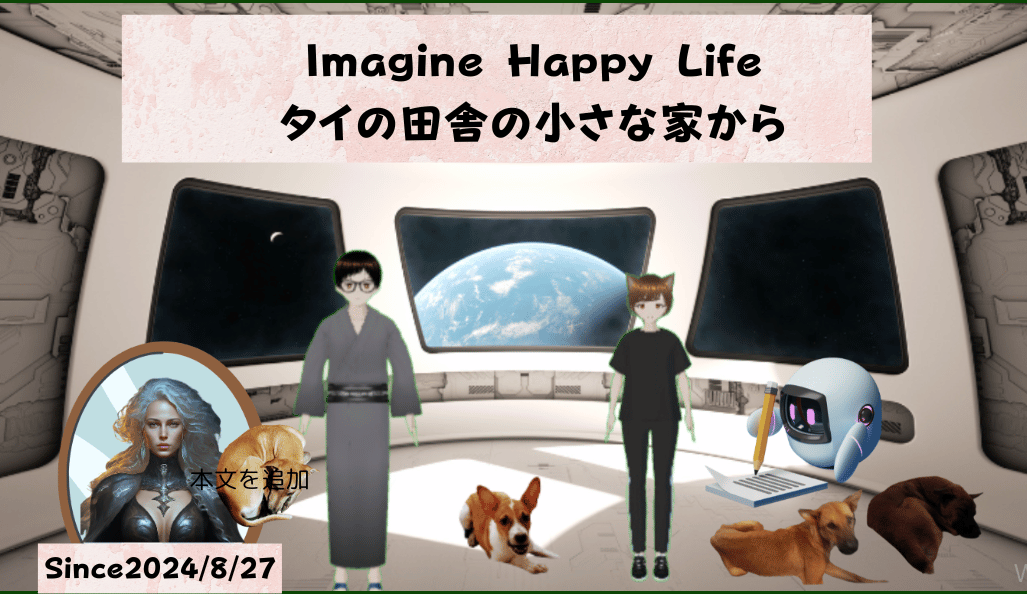この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場所、事件等は著者の想像によるものです。実在のものとは一切関連がなく、また、実際の出来事に基づくものではありません。
異境の囁き―バンコク怪奇譚1 『バンコクの呪われた扇風機』
バンコク怪奇譚2 『恐怖の虫喰い寺院』
異境の囁き―バンコク怪奇譚3 バンコクの黒犬伝説 – 恐怖の深夜タクシー
桜田一郎は、東京の大手広告代理店で働くエリートサラリーマンでした。しかし、バブル崩壊後の経済不況で会社が大幅なリストラに踏み切り、一郎もその負の連鎖に巻き込まれてしまいました。自信を失い、将来への不安にも苛まれる日々でした。落ち着くまでの数ヶ月間、安住の地としてバンコクを選んだのです。
一郎は落ち着くまでの数ヶ月間、安住の地としてバンコクを選びましたが、慣れない土地で言葉も通じず、孤独に苛まれていました。誰にも頼ることができず、自分一人で全てを切り開いていかなければならないというプレッシャーが、一郎を精神的に追い詰めていく状況でした。言葉の壁と文化の違いに加え、経済的な不安もあり、不安と恐怖に押しつぶされそうになっていました。
一郎が住んでいたのは、クローン運河沿いのラーマ4世道路沿いの古びたアパートでした。かつてこの一帯はタイ王朝の中心地であり、運河の暗渠には祟り神が棲み着くと言われていました。一郎を気味悪がる黒犬の正体も、実はこの地に伝わる亡霊の犬の伝説につながっていたのです。
アパートの隣には、地元の人が飼っている黒い犬がいました。その犬はいつも一郎を睨んで吠えていました。
一郎は子供の頃、家の近くをうろついていた野良犬に襲われた嫌な体験がありました。大人しく遊んでいたはずの一郎に、突然吠え狂う獰猛な犬が襲いかかり、腕に深手を負わされたのです。それ以来、犬を見ると無意識のうちに体が硬直し、あの時の恐怖がよみがえってくるのだでした。一郎は表面上はその恐怖を克服しているふりをしていましたが、深層心理には犬への強い潜在的な恐怖が刷り込まれていたんのです。
(一郎の心のつぶやき)
「なんだろう、あの犬は。いつも私を睨んでは吠えるんだ。私は犬が嫌いじゃないけれど、あの犬は何か不気味な感じがする。」
夜深く、一郎はアパートの前でタクシーを待ち構えておりました。アパートの前の道は突き当りが運河となっている寂れた場所でした。普段ならタクシーが止まっているのですが、その日はタクシーは来ませんでした。
深夜の静けさの中、一郎の影は亡霊のようにちらちらと揺らいでいました。周りの家々は闇に閉ざされ、一筋の灯りも見えませんでした。ただ遠くの橋の下から、運河の水音が冷たく淀んだ気配を運んでくるばかりでした。一郎は運河の彼方に潜む何かに気づいたような気がしました。生気を持たぬ者が、この世ならざる領域からのぞいているように思えたのです。
時折、枯れ葉が路上を舞う度に、一郎は戦慄を覚えずにはいられませんでした。タクシーが来る気配はなく、ただ闇が一郎を飲み込もうとしているかのようでした。やがて遠くで不気味な物音が聞こえてきます。それは獣のような荒い啼き声なのか、それとも…
トッケーが4回鳴きました。そのあと、野良犬たちの遠吠えが次第に増えてきました。一郎は、野良犬たちに取り囲まれ、恐怖に包まれました。
(一郎の心のつぶやき)
「ひっ、な、なんだこれは!? 野良犬どもに囲まれてしまった。逃げ道がない!」

画像提供:Being
彼らは一郎を直接襲う気配はなく、静かに佇んでいましたが、その圧倒的な存在感だけで一郎の心は恐怖で震えました。不気味な沈黙の中、野良犬たちの目が一斉に赤く光り始め、まるで暗闇を切り裂く血のようでした。その赤い輝きが次第に増すごとに、一郎の胸の内はさらなる恐怖で満たされていきました。夜の静寂が、犬たちの恐ろしい目と一郎の高鳴る鼓動だけが響く場となっていました。一郎は恐怖に包まれました。すると、野良犬たちの目が次第に赤く光り始めた。赤い目が増えるにつれ、一郎はますます恐怖に陥っていきました。
すると、その中のアパートの隣の黒い犬が突然一郎に飛びかかってきました。一郎は驚いて後ずさりしましたが、間に合いませんでした。
「ぎゃああああっ!」
犬は一郎の腕に噛みつきました。一郎は悲鳴を上げて犬をけ振り払おうとしましたが、犬は離れませんでした。一郎は血を流しながら、誰か助けてくれと叫びました。
幸いにも、近くにいたタクシーの運転手が駆けつけてくれました。
「大丈夫ですか!?」運転手が叫びました。
彼は犬をけ蹴り飛ばして、一郎を車に乗せてくれました。
一郎(血を拭きながら)「あ、ありがとうございます。病院に、病院に行ってください。お願いします。」
運転手「かしこまりました。」
一郎は感謝の言葉も言えないまま、彼に病院に連れて行ってくれるよう頼みました。彼はうなずいて、急いで運転し始めました。
一郎は車の中で傷口を押さえながら、なぜあの犬が一郎を襲ったのかと考えました。一郎はその犬に何も悪いことをした覚えはありませんでした。ただ、その犬の目には、一郎に対する憎しみと殺意が見えたような気がしました。それはまるで、エドガーアランポーの「黒猫」に出てくるような目でした。
「あの目を見る限り、あの犬は私を憎んでいるようだった。まるで復讐心に燃えているかのように…」
一郎はそんなことを考えながら、タクシーの運転手に話しかけようとしました。
「すみません、運転手さん。」
しかし、彼は無言で運転していました。一郎は彼の顔を見ようとしましたが、暗闇の中ではよく見えませんでした。ただ、彼の目だけが赤く光って見えました。
奇妙なことに、その隣の席には、色褪せた黄色の扇風機が置かれており、運転手を静かに見守っていました。その古びた扇風機の羽根は、不吉な印象を与えるナチスの紋章のようでした。不思議なことに、電源が接続されていないにもかかわらず、扇風機の羽根はゆっくりと、しかし絶え間なく回転を続けてました。その動きは、まるで風の存在を感じさせない閉ざされた空間において、時間が凍りついたかのような静寂の中で、ひっそりとその場の空気をかき乱していました。

画像提供:Being
その時、一郎は恐ろしいことに気づきました。
(一郎の心のつぶやき)
「ま、まさか…あの運転手の目は、あの黒い犬と同じ赤い目だ!これは一体…!?」
一郎は怯えました。
「運転手さん、貴方の目が赤く光っているんですが…?」
運転手は無言のままでした。
一郎の不安は高まる一方でした。
(一郎の心のつぶやき)
「なんなんだ?この恐ろしい状況は!あの黒い犬に噛まれて、それから赤い目の奇妙な運転手に…。まさか、私は何か恐ろしいことに巻き込まれたのか?」
一郎の疑心暗鬼は次第に募っていきました。しかし、逃げ出す術もありません。彼は恐怖に押しつぶされながらも、なんとか病院に着くことだけを願っていました。
やがて病院に到着すると、運転手はぴたりと止まり、ドアを開けて降りていきました。そして夜の闇に消えていったのです。
一郎は運転手の背中を見送りながら、ひとり震えていました。
気がつくとタクシーの車も消えていました。
(一郎の心のつぶやき)
「一体、あの運転手は何者だったんだ?正体が分からない…。でも助けられたことに感謝しないといけない。とにかく早く治療を受けなくては。」
傷口から血を流しながら、一郎はようやく病院に入っていったのでした。
しかし、実は運転手の正体など知る由もありませんでした。目撃されることのない使者が、病院までの道連れを果たしたに過ぎなかったのです…。
一郎が病院の門をくぐり、血を流しながら救助を求めたその瞬間、不気味な静寂が周囲を包み込みました。しかし、彼が一歩病院の中に踏み込むこともなく、赤い目をした運転手に再び捕まってしまいます。運転手は何の説明もなく、一郎を車に押し込みました。
車の中、後部座席にはすでに一郎を待ち受けていたかのように、獰猛な黒犬がいました。一郎が絶叫する中、黒犬は彼の腕を激しく噛みつきます。「なぜだ…!なぜこんなことが…!」彼の絶望の叫びは、運転手の無言の運転に呑み込まれていきました。
そして、予期せぬ瞬間に車は暴走を始め、直進して運河に突っ込みました。水しぶきが高く舞い、車は川底へと沈んでいきます。一郎は窒息しながらも窓ガラスを叩き続けましたが、その時、不気味な赤い光が彼を包み込みます。無数の野良犬の赤い目が、水面から彼をじっと見つめていました。
「誰か…助けて…!」彼の叫びは、運河の暗闇に吸い込まれていきました。
足音が響き渡り、その主が姿を現します。水に濡れた長い黒髪を持つ、恐ろしいほど美しい”バンコクの黒い乙女”の亡霊です。「罪深き者よ、神にも見放された哀れな魂。この世の苦しみからは逃れられない!」乙女は冷たい声で言葉を投げかけます。

画像提供:Being
彼女の手が水面に触れると、野良犬たちが一斉に一郎に襲いかかります。「これが、お前の運命だ!」乙女の声が響き渡る中、一郎の絶叫が夜の闇に消えていきました。
翌朝、警察が到着した時、運河にはただ無数の野良犬が騒がしく集まっているだけでした。遺体は一つも見つからず、まるで悪魔の祭典が行われたかのような恐ろしい静けさが残されていました。
一郎はぐっすり眠っていましたが、突然悲鳴のような声で目が覚めました。冷や汗をかきながら見渡すと、病室の薄暗い隅から怪しい影が這い出してくるのが見えました。
「お、おい…誰だ!?」
声を上げると影は一瞬形を変え、看護婦の姿になりましたが、そのあまりにも不気味な表情に一郎は戦慄しました。看護婦は口を覆うように手を当て、けれども指の隙間からにじみ出る黒い液体のような物体に一郎の視線は釘付けになってしまいました。
「罪深き者よ…」
低く荒れた呼吸が聞こえ、次第に看護婦の姿は歪んでいきます。やがてその姿は完全に別の生物へと変貌を遂げました。漆黒の肌に蛇のような赤い眼、恐ろしい牙を剥いた形相です。一郎は叫びもできずにただただ震えるばかりでした。
「神にも見捨てられしこの世の呪われた魂よ…貴殿の苦しみはこれからはじまるのです…」
その気味悪い饒舌な声が一郎の脳裏に徐々に食い込んでいき、意識が遠のいていくのを感じる中で、一郎は自分の理性が狂いそうになっていくのがわかりました。
病院に入り治療を受けた後、一郎は自らの体験したできごとを捜査願いを出そうと警察に赴きました。
警察官「具体的にどのようなことがあったんですか?」
一郎「実は深夜にタクシーを待っていた時に、野良犬に取り囲まれて、そのひとつの黒い犬に腕を噛まれたんです。近くにいたタクシーの運転手が助けてくれたのですが、その運転手の目が不気味な赤い光を放っていたんです。まるで、あの黒い犬と同じような目で…」
警察官「なるほど、非常に恐ろしい体験をされたんですね。野良犬に襲われるケースは多々ありますが、運転手の目が光っていたということは異例の出来事です。」
一郎「そうなんです。あの運転手の正体が分からず、とても不安なんです。あの目は決して人間のものとは思えなかった…」
警察官は一郎の証言を慎重に聞き、捜査を開始しました。しかし、結局あの夜の運転手の行方は謎のままでした。
一方、アパートの近所に住む人々に聞き込みを行うと、意外な証言が得られました。
モタサイバイクタクシーのブンおじさんは年よりの小柄なタイ人男性です。しわくちゃの作務衣姿で、頭にはタクシー運転手によくみられる迷彩柄の野球帽を被っています。
「ああ、あの黒い犬のことですか?あれは実は、この辺で起きた残虐な殺人事件の犠牲者の魂が宿ったという噂なんですよ。」
隣人の大学生エーは華奢な肢体と精悍な顔立ちのタイ人の学生です。パンクロックファッションが割と奇抜で、赤や黒のタイダイ染めのTシャツにスタッズ付きのジーンズを好んで着用している。
「毎晩あの犬の遠吠えが聞こえるんですが、それは殺された人の怨念の声なんだと言われています。」
一郎「(血の気が引いた)な、なんとまあ…」
日が経つにつれ、一郎は心的トラウマに加え、前世でその黒い犬を虐殺したのではないかという強迷観念に囚われるようになっていきました。
さらに管理人の不気味な老婆レックに聞くと、その辺りでは”赤い瞳の男”が現れる奇怪な話が出回っているということでした。
レック「赤い瞳の奴に出くわすと、不思議な病に冒されるか、最悪の場合は命を落とすっていうんですよ。実はあんたが住む部屋では、前に日本人の不動産屋の社長が階段から落ちて死んだり、ファーランのバックパッカーが発狂したりした不気味な出来事があったんです。その始まりは、この近所で起きた衝撃的な殺人事件がきっかけじゃないかと噂されてるんですよ。」
一郎「殺人事件って…?」
タイ北部の山岳少数民族出身の老婆は階段から落ちた人の死体を見つけた際、血が轟いた思いがしたそうです。その後、奇怪な夢を見るようになり、赤い瞳の男の存在を確信するようになったそうです。
レック「あの男は私の夢に現れては、殺人現場を指差して、ニヤニヤと冷笑を浮かべるのです。あの事件の黄色い扇風機も赤い瞳と一緒に夢に出てくるのよ」
その黄色い扇風機は、ある夜、自宅で夫からのだらしない暴力に耐えかねた妻によって使われた凶器でした。夫は長年にわたり妻に対して精神的、肉体的暴力を振るってきました。しかし、その日、妻は逆ギレしてしまい、手近にあった黄色い扇風機で夫を撲殺してしまいます。事件は一転して妻の逮捕に至り、地域社会に衝撃を与えました。夢に現れる赤い瞳の男と黄色い扇風機は、その残忍な事件の象徴として、レックの心に深く刻まれたのでした。
一郎は払拭しきれない不安に怯えました。そんな折、隣人の黒犬が捕獲され、病院に連れてこられました。獣医から衝撃的な事実が明かされました。
「この犬は命にかかわる重傷を負っています。しかし、傷の原因となった人を憎み呪っているかのように、誰にも近寄らせません」
一郎は胸が締め付けられる思いがした。自分が呪われていると確信したのです。
数日後、一郎は運河の曲がり角で、凶悪な弾丸によって命を奪われました。
振り返ると、そこには目深く陥ったような恐ろしい顔つきの男がいました。彼は酷く削げた顔立ちで、まるでタイ史上最悪の殺人鬼集団”マイペンライ兄弟”の生き残りのようでした。彼は一郎に対して、祟りの報復という含みを持つ細い目つきを向けました。ただし一言も発しませんでした。そして突然、音を立ててはいけないと示すような仕草で、銃を取り出しました。
そして一言、「お前は忠告を無視して真夜中に扇風機を止めなかっただろ、罪を償え」
夜の闇に紛れる間もなく、彼の体は冷たいアスファルトに横たわり、血は静かに川へと流れていきました。目が暗闇に慣れると、彼の視界には一際異様な光景が映りました。そこには一匹の黒犬が、その魂を抜かれたかのように無残にも死んでいました。その犬の傷口からは、まるで生命の終焉を告げる鐘の音のような静寂が漂っていました。
一郎の生命が少しずつ薄れゆく中、彼の瞳に映るものは、死の底からの使者ともいうべき、燻るような赤い瞳でした。遠くの闇からじっと彼を見つめるその瞳は、何世紀にも渡って獲物を狙う獰猛な獣の目であるかのようでした。その視線は、彼の魂を凍りつかせる冷たさで、死の恐怖を倍増させました。そして、一郎はその赤い瞳と共に、この世の闇へと静かに溶けていきました。
この怨霊の物語は、バンコクの新たな伝説となり長く語り継がれることとなりました。

【新パヤナーク戦記】