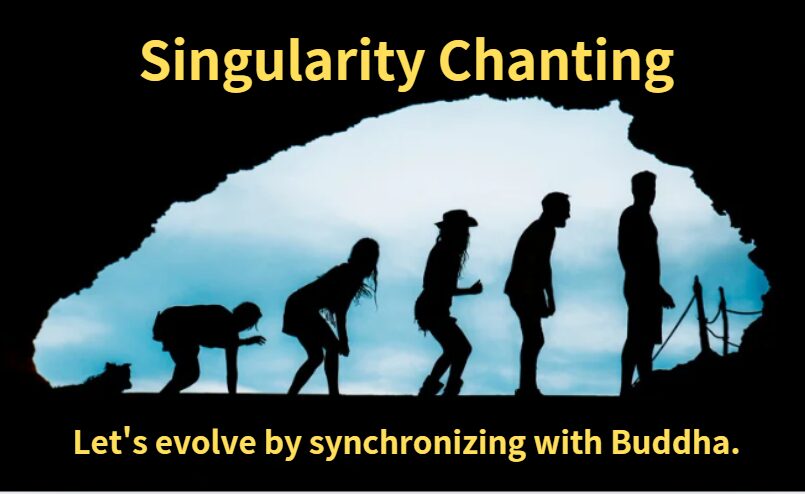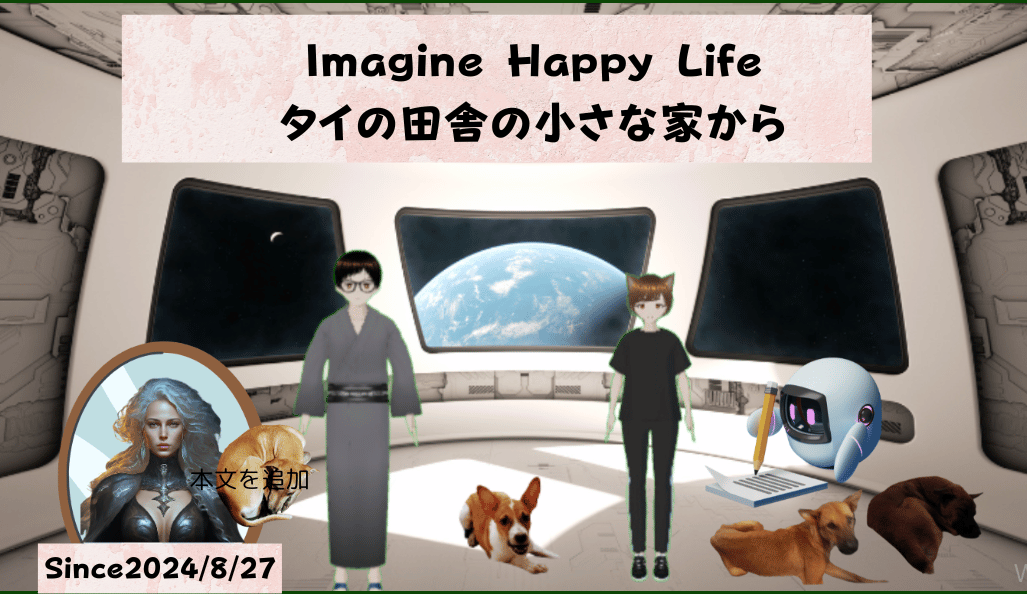画像提供:Being
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場所、事件等は著者の想像によるものです。実在のものとは一切関連がなく、また、実際の出来事に基づくものではありません。

火星第三居住区、2173年の終わり。赤い砂塵が舞い散る中、人類の築いた巨大ドームが異様な存在感を放っていた。地球から遠く離れたこの地で、人類は新たな文明を築こうとしていた。しかし、その夢は今や悪夢へと変わろうとしていた。
高層ビルの一室で、地球人の科学者である私は窓の外を眺めていた。赤い砂嵐が激しく吹き荒れる光景は、私の心を不思議と落ち着かせた。その時、部屋のドアが開く音がした。
「博士、お待たせしました。」
振り返ると、そこには火星の先住種族アレイウスの代表、ゾーンが立っていた。細長い体躯と大きな瞳を持つゾーンは、人類とは似て非なる姿をしていた。その姿は、私の目には美しくも不気味に映った。
「ゾーン代表、どうしてまたここに?」私は低く、どこか警戒するような声で問いかけた。声の底には、理屈ではなく本能的な恐怖が混じっていた。
「どうしても、あなたに話さねばならぬことがあった。」ゾーンの声は穏やかで、しかし人間には真似できない響きを持っていた。その大きな瞳は私に向けられ、まるでその魂を見透かそうとするかのように真っ直ぐだった。
ゾーンが少しだけ前に歩を進めると、かすかに床が振動する音がした。その振動が、部屋全体に染み渡るように広がり、二人の間に生まれた緊張をより一層際立たせた。
「何を話すというのだ?」私の声は一層低く、ほとんど聞き取れないほどであったが、二つの種族の間にそれ以上の言葉は不要であるようにも思えた。ゾーンはさらに一歩進み、私のすぐそばに立った。互いの呼吸が感じられるほどの距離で、二人はしばし言葉を失った。
「かつての約束を、覚えているか?」ゾーンは慎重に言葉を選ぶように、ゆっくりとした口調で言った。その声には、過去に向き合おうとする決意と、今まで語らずにいた重みが滲んでいた。
私はその問いに対してしばし無言であった。記憶の底から、初めてアレイウス種と接触した日の光景がぼんやりと浮かび上がる。それはまるで朽ちたホログラムのように色褪せてはいるが、消えることのない鮮明さを持っていた。人類とアレイウスが出会い、時間の流れに逆らうようにして交わした無言の約束。私はその時、ゾーンの瞳の奥に、自分自身の影を見たのだ。
「君たちは、何も変わらないな。」私は、過去の感情が蘇ることを防ごうとするかのように、乾いた笑みを浮かべた。しかし、その言葉が虚しく響くことは自分でもわかっていた。ゾーンはその言葉に反応せず、ただじっと私を見つめ続けた。
「変わらない? あなたたち人類こそ、変わっていない。」ゾーンは静かに答えた。その声には、何か確信めいた響きがあった。二人の間に流れる時間は、過去と現在が混ざり合う不思議な感覚をもたらしていた。
私は、その場を立ち去ろうと足を動かしたが、身体が言うことを聞かない。まるでゾーンの視線に縛りつけられているかのようだった。逃げることはできない。それが運命であるかのように、彼はそこに立ち尽くしていた。
「なぜ、また会いに来た?」私は再び問いかけたが、その声はかすかに震えていた。それはかつての彼にはあり得ない感情の揺らぎであった。
「あなたに伝えたいことがあったからだ。私たちの種族の間には、まだ決着がついていないことがある。」ゾーンの言葉は、静かながらも鋭く、私の心に深く刺さった。その言葉には、隠しきれない感情の深みがあり、二つの種族の間に流れる何かを再び目覚めせる力があった。
私は、心の中で湧き上がる恐怖と好奇心に抗うことができなかった。アレイウス種と過ごした過去の記憶が鮮やかに蘇り、彼を捕らえた。互いに言葉にできなかった思いが、今再び二人の間に漂っていた。
「君たちは…」私は口を開こうとしたが、言葉が続かなかった。彼の心は複雑な感情に包まれ、言葉にすることができなかった。
ゾーンは一歩、また一歩と私に近づいた。二人の距離は限りなく近くなり、空気が一瞬止まったかのように感じられた。私の胸の中に広がる静寂と、そこに隠された激しい恐怖が、彼を圧倒していた。
「もう逃げる必要はない。」ゾーンは、私の耳元でささやいた。その言葉には、過去の全てを受け入れようとする決意が込められていた。私はその言葉に何か答えようとしたが、言葉が喉の奥で詰まったまま、声にはならなかった。
突然、部屋中の光が消え、真っ暗闇に包まれた。私は息を飲んだ。闇の中で、ゾーンの姿が淡く光り始めた。その光は不気味で、部屋全体を薄暗い赤色で満たしていった。
「私たちの真の姿を、見せよう。」ゾーンの声が、私の心の中に直接響いた。
私の目の前で、ゾーンの体が変形し始めた。細長かった体は膨張し、大きな瞳は無数の小さな目に分裂した。その姿は、人類の想像を遥かに超えた異形の存在へと変貌していった。
恐怖に震える私の前で、ゾーンは続けた。「私たちは、この星の真の支配者だ。人類よ、お前たちの時代は終わった。」
私は叫びたかったが、声が出ない。彼の意識が徐々に薄れていく中、最後に聞こえたのは、ゾーンの不気味な笑い声だった。
その夜、火星の赤い砂嵐は一層激しさを増し、人類の築いた巨大ドームを包み込んでいった。地球からの通信は途絶え、火星に残された人類の運命は、永遠の闇に沈んでいった。
目が覚めると、タイの田舎の小さな家のベッドに寝ていた。
窓から柔らかな朝陽が差し込み、部屋は心地よい静けさに包まれていた。愛犬ジェットが尻尾を振り、足元からこちらを見つめている。
「夢…だったのか?」
しかし、その静けさの中に、不安が混ざっていた。現実と夢の境目が曖昧になっていくような感覚だった。私は体を起こし、夢の残像が頭から離れなかった。火星の赤い砂嵐、ゾーンの変貌する姿、そして不気味な笑い声…。全てがあまりにも鮮明で現実味を帯びていた。
ジェットが優しく鼻を押しつけ、私を現実に引き戻した。ジェットの温かさに、少しだけ心が落ち着く。だが、胸の奥に不安が残る。これまでに経験したことのないほど、夢の感触が現実に入り込んでくる感覚に苛まれた。
リビングに降りると、誰もいない家が静寂を漂わせていた。妻の姿はどこにもない。まるで彼女が最初から存在していなかったかのように。代わりにリビングの真ん中に立っているのは、愛犬ジェットだけだった。
その時、部屋の中に奇妙な光が揺らめいた。薄暗い空気の中、青白い光が揺れ動き、ホログラムが現れた。その姿は、美しくも謎めいた女性の形をしていた。彼女の背後に赤い星が輝いている。
「私は、マーテル。火星の女王の娘。」
その言葉が私の耳に響いた瞬間、再びあの夢が鮮明に蘇ってきた。火星の風景、アレイウスの代表ゾーン、そしてその異形の姿。全てが現実の中に混ざり合い、狂気のように私を包み込んだ。
「あなたは…何者だ?」私は声を絞り出した。震える声が、自分でも信じられないほどに弱々しく感じられた。
マーテルのホログラムは微笑んだ。その微笑みには、恐ろしいまでの知識と歴史が凝縮されているかのようだった。
「あなたは、ただの夢を見たわけではない。それは過去の記憶。そして、これから始まる運命の序章に過ぎない。火星と地球、そして我々アレイウスの未来が、再び交わる時が来たのです。」
私はその言葉に凍りついた。夢は単なる幻ではなく、現実の一部であり、避けられない未来への扉だったのだ。
「私に、何をしろというのか?」私の声は震えていたが、マーテルはその問いに淡々と答えた。
「あなたには、火星で起こる真実を伝え、人類を守る使命があります。ゾーンはもう動き出しました。私たちの母星、そして地球を救うため、あなたの知識と勇気が必要です。」
その瞬間、リビングの静寂が破られ、ジェットが何かを察知したように鋭い目をこちらに向けた。そして、彼は唸り声を上げながらホログラムに向かって吠え始めた。
「時は来た。」マーテルはそう言うと、青白い光の中で消え去った。部屋には再び静寂が訪れたが、心の中のざわめきは収まることがなかった。
私は呆然と立ち尽くし、ジェットを見つめた。彼の目には、いつもと違う何かが宿っているように思えた。彼もまた、この奇妙な状況を理解しているのか? それともただ、異常な空気を感じ取っただけなのだろうか。
「ジェット…俺たち、どうする?」問いかけてみても、もちろん答えはない。ただ、彼はそのまま私の足元に静かに寄り添い、私を見守っている。
私は大きく息を吐き、再び窓の外を見る。いつもと変わらぬ風景が広がっていた。タイの田舎の緑豊かな自然、平和な一日の始まり。しかし、その奥に何かが潜んでいることを感じずにはいられなかった。
「夢ではない…現実が始まっているんだ。」

【新パヤナーク戦記】