
画像提供:Imagen3

画像提供:Chat GPT
ここがポイント
[balloon_left img=”https://jiyuland.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-21_03-22-31.png” caption=”Tensui”]
プラカノンの運河にまつわるこの怪異は、街の人々の間で語り継がれ続けた。特に夜になると、不気味な風が運河沿いを吹き抜け、誰かの家の中からかすかに扇風機の羽音が聞こえてくるという噂が広がった。その音を聞いた者は、やがて奇妙な夢に悩まされ、夢の中では見知らぬ装置たちが彼らに語りかけてくると言われていた。
老女はもう姿を見せることはなくなったが、その忠告は運河沿いの住人たちの間で静かに守られていた。「あの黄色い扇風機を決して動かしてはいけない」――それが唯一の防衛策であり、運河の底に眠る怨念を呼び覚まさないための最後の手段だと信じられていた。
それでも、扇風機の前を通りかかるたびに、今でも人々は背後に冷たい風を感じると言う。まるであの世から、まだ何者かがこちらを見つめているかのように。
[/balloon_left]
プロローグ プラカノンの運河にて
それは、バンコクの喧騒からわずかに離れた場所にあった。都市の熱気と人々のざわめきから逃れ、私が足を踏み入れたのはプラカノンの運河沿い。そこはただ静かに、どこか薄暗く、時が止まっているかのような場所だった。濁った水面には、まるで運河そのものが私を引きずり込もうとするかのような陰鬱な雰囲気が漂っていた。
道沿いには古びた木造家屋が並び、その一つ一つが、過去に取り残された記憶の断片のようだった。運河の水面を覆う薄い霧が立ち込め、葉やゴミが浮かんでいるのを目にするたびに、私は何か不気味なものに取り憑かれたかのような感覚を覚えた。そして、運河沿いを歩いていると、視界の端にそれが見えた――古びた黄色い扇風機が一台、ほこりをかぶりながら家の前に置かれていた。
その扇風機は、いかにも使い古され、かつては誰かの生活を彩っていたかもしれないが、今やその役目を忘れ去られたかのように放置されていた。私の目は、なぜかその無機質な物体に引きつけられた。古びた鉄製の羽根が黄色に錆びつき、薄汚れたコードがだらりと床に垂れ下がっていた。その風景は、他のどんなものよりも異様に感じられた。
その家は、外見からしても長らく誰も住んでいないことがわかった。壊れかけたドアの横で、その扇風機はまるで見張り番のようにじっとしていた。私はその異様な扇風機に近づくことをためらった。だが、どうしてもその古い黄色い扇風機から目を離すことができなかった。
「あの扇風機をつけてはいけない」――
その時、後ろから低い声が聞こえた。振り返ると、市場で出会った老女が立っていた。彼女は以前、私に運河の話をした人物で、その目は鋭く私を見据えていた。
「なぜ…?」私は尋ねたが、老女は答えなかった。ただ、沈黙のまま運河の方を指差した。
その瞬間、私は何かを感じ取った。運河の水面が揺らぎ、風もないのに、扇風機の羽根がわずかに動いたのだ。何かが、この場所に潜んでいる――そう確信するには十分だった。
私は、家の中に入るべきではないとわかっていた。だが、不思議なことに、足が勝手に動き、扉の前まで近づいてしまった。扉の先には何が待ち受けているのか、まるで運河の底に潜む得体の知れないものが、私を引き込もうとしているかのような感覚が拭えなかった。
家の中に入ると、奇妙な湿気が私を包んだ。薄暗い部屋の片隅には、家具が乱雑に積み重ねられていた。そして、視線は再びあの黄色い扇風機へと向かっていた。なぜか、部屋の中央にあったのだ。ついさっきまで外にあったはずの扇風機が、今やその場に鎮座している。
冷や汗が背中を伝った。私は思わず後ずさりし、外へ逃げ出そうとしたが、足が動かなかった。部屋の中に奇妙な風が吹き込んできた。窓は閉じられているはずなのに、扇風機の羽根がゆっくりと回り始めたのだ。その羽根が回るたび、どこからともなく、耳をつんざくような音が聞こえてきた。
「この扇風機が回る時…魂が彷徨うんだよ…」
再び老女の言葉が頭をよぎった。私はその言葉を思い出し、目の前で回り続ける扇風機を止めなければならないという衝動に駆られた。だが、体が動かなかった。まるで扇風機の風が私の全身を縛り付けるかのように、動けなかったのだ。
羽根の回転が速くなるたびに、運河の外から聞こえてくる波の音が、ますます大きくなっていった。私の耳には、人々の囁き声が混じり始め、それが次第に悲鳴のように聞こえてきた。やがて、私はその声がどこから来ているのかに気づいた――それは運河の底から響いていたのだ。
突然、扇風機がピタリと止まった。部屋の中に張り詰めた静けさが戻ったかと思うと、足元から冷たい風が這い上がってきた。まるで何かが私の足元にいるかのようだった。運河の底に沈んだ者たちの怨念が、この家と扇風機に宿り、私を引きずり込もうとしている――そんな感覚が私を支配した。
その瞬間、私は何とか体を動かし、部屋を飛び出した。後ろで扇風機の羽根が再び回り始める音が聞こえたが、私は振り返らなかった。逃げ出す足は、地面に触れるたびに重く感じたが、何とか運河から遠ざかることができた。
老女の姿は、いつの間にか消えていた。静かな運河のほとりで、私はただ立ち尽くし、背後に迫る恐怖から逃げ切れたことに感謝した。しかし、あの古い黄色い扇風機が未だにこの運河沿いに置かれ、夜ごとその羽根が回るたびに、運河の底から何かが這い上がってくるような気配を感じずにはいられなかった。
第一章:灼熱の夏
プラカノン運河の水面は、容赦ない太陽の光を反射し、まばゆいばかりの輝きを放っていた。運河沿いの小さな木造家屋の中は、重苦しい空気に包まれていた。サオワパーは、家の中で一人、古びたうちわを必死に仰ぎながら「暑い、暑い」と繰り返していた。
その日、彼女は庭先で奇妙な光を放つカブトムシを見つけた。普通のカブトムシとは違い、その甲羅は青みがかった光沢を持っていた。極度の空腹と疲労に苛まれていた彼女は、思わずそのカブトムシを手に取り、口に入れてしまった。
それが全ての始まりだった。
第二章:幻覚の始まり
その夜から、サオワパーの世界は一変した。暗闇の中で、彼女は不思議な装置を目にするようになった。それは大きな羽根が回転し、涼しい風を送り出す機械だった。現代の扇風機に似ているその装置は、彼女の目の前で優雅に回転しながら、不思議な言葉をささやきかけた。
「我々は風の精霊…あなたに安らぎを与えましょう…」
装置から漂う涼しい風は、確かに彼女の肌に触れた。しかし、それは現実には存在しないはずのものだった。サオワパーは次第にその幻影に魅了されていった。
第三章:深まる狂気
幻覚は日に日に強くなっていった。風を送る装置は増え続け、時には部屋中を飛び回るようになった。それらは様々な声で彼女に語りかけた。
「あなたの苦しみを知っています…」
「私たちと一緒に来ませんか…」
「この暑さから解放してあげましょう…」
サオワパーは、その声に慰めを見出すようになっていた。現実の暑さと孤独から逃れるように、彼女は幻覚の世界に没入していった。
第四章:赤ん坊の死
ある日、彼女は赤ん坊の泣き声で目を覚ました。しかし、幻覚の中の装置たちは異様な音を立てて回転していた。
「子供はもういらない…私たちがいれば十分…」
装置たちの声に導かれるように、サオワパーは赤ん坊の世話を怠るようになっていった。そして、ついに赤ん坊は高熱で命を落としてしまう。しかし、彼女の歪んだ現実認識は、その事実すら受け入れることができなかった。
第五章:最後の幻覚
幻覚は最後の段階に入った。風を送る装置たちは、より大きく、より鮮やかになった。それらは部屋中を埋め尽くし、竜巻のような風を巻き起こすようになった。
「もう十分です…私たちと永遠に…」
彼女は高熱に苦しみながら、最後の言葉を発した。
「涼しい…とても涼しい…」
そして、サオワパーは息を引き取った。
第六章:幽霊となって
死後、サオワパーの魂は安らぐことなく、プラカノン運河のほとりをさまよい続けることになった。しかし、彼女の幽霊が見せる幻影は、生前の幻覚とは違っていた。人々の目には、彼女は赤ん坊を抱いた姿で映り、「暑い、暑い」と繰り返すのだった。
第七章:戦争から帰還した夫
数ヶ月後、戦争から帰還したソムチャイは、妻と子の死を知らされる。彼が家に戻ると、そこには奇妙な風の音が響いていた。
運河沿いで、彼はサオワパーの幽霊と対面する。彼女の周りには、かすかに青白く光る風の渦が見えた。それは彼女が生前見ていた幻覚の名残のようでもあった。
「なぜ私たちを置いて行ったの?」と彼女は叫んだ。
ソムチャイは幽霊に取り憑かれ、運河の中へと消えていった。人々は、その夜、運河の上で奇妙な風が渦を巻いていたと語る。
エピローグ:伝説となって
それから何年も経った後も、プラカノン運河のほとりでは、夜になると奇妙な風と共に「暑い」という女性の声が聞こえるという。時には、青白い光を放つ不思議な機械の幻影が目撃されることもある。
村人たちは、サオワパーとソムチャイの悲劇的な物語を語り継いだ。それは単なる幽霊譚ではなく、戦争による家族の離散、孤独、そして狂気がもたらす悲劇の物語として伝えられている。
特に暑い夜には、運河の上で青白い光の渦が見えることがあるという。その光の中には、時折、風を起こす奇妙な装置の形が浮かび上がるという。しかし、決してその光に近づいてはいけない。もし近づけば、サオワパーの幽霊に魅了され、運河の中へと引きずり込まれてしまうかもしれないのだ。
プラカノン運河の幽霊の伝説は、狂気と現実の境界があいまいになった時、人の心がいかに脆くも壊れやすいかを物語る警鐘として、これからも語り継がれていくだろう。そして、暑い夜に運河のほとりを歩く人々は、今でも背筋に冷たいものを感じるのである。

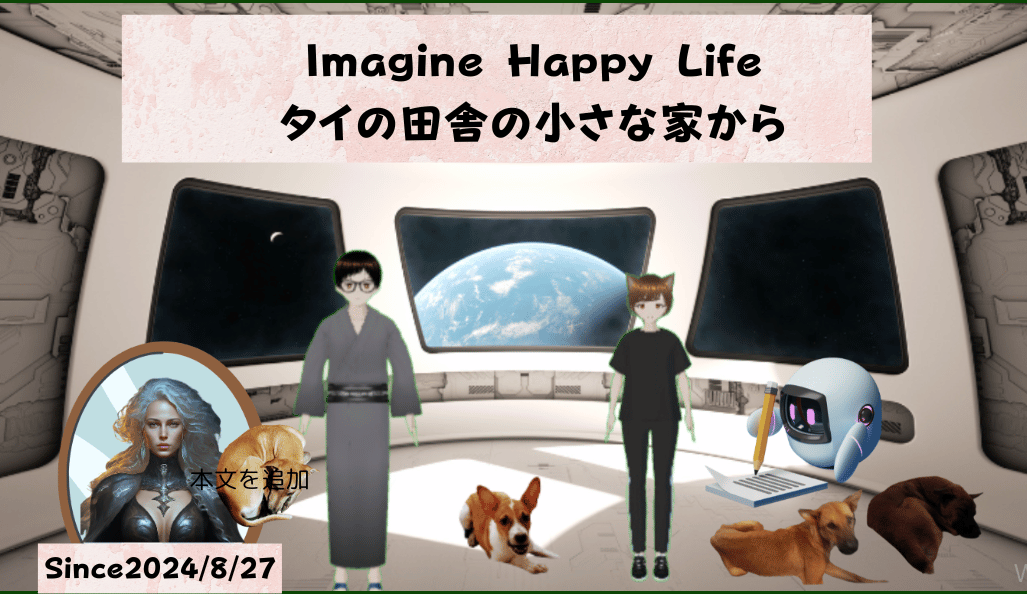

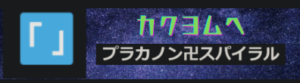


コメント