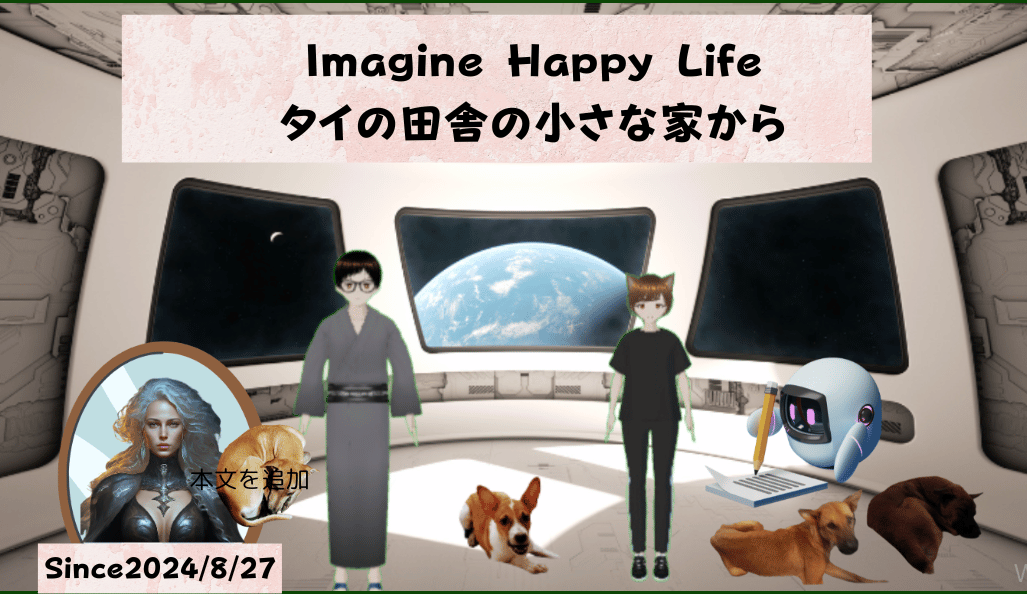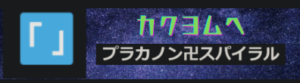画像提供:Chat GPT

画像提供:Chat GPT
[balloon_left img=”https://jiyuland.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-21_03-22-31.png” caption=”Tensui”]山田長政の物語を執筆しながら、彼の『やってみにゃあわからねえ』という前向きな姿勢に、私も励まされました。400年前に異国の地で、言葉も文化も違う環境に飛び込んでいった彼の勇気。そして何より、その地で多くの人々と心を通わせ、信頼を築いていった人間力に感銘を受けます。現代を生きる私たちにも、彼の生き方から学べることがたくさんありそうです。#山田長政 #歴史小説 #アユタヤ王朝[/balloon_left]
第二章:タイとの出会い (第1部)
アユタヤの港に降り立った山田長政は、熱気と喧騒に包まれた異国の地を目の当たりにした。船から降りると、むっとする蒸し暑さが彼を包み込む。長い航海で慣れたはずの揺れが、まだ足元に残っていた。
「おっと、あぶねえや」
長政は踏ん張りながら、周囲を見渡した。色とりどりの衣装を纏った人々が行き交い、見慣れない果物や香辛料の匂いが鼻をくすぐる。異国情緒あふれる光景に、長政の目は輝いていた。
「へえ、こりゃあ面白えじゃねえか」
彼の傍らには、同じく日本から渡ってきた商人の一人、佐藤源左衛門がいた。
「長政どの、あんたは本当に怖いもんしらずだね。おいらなんぞ、こんな知らん土地で暮らすなんて考えただけで足がすくむわ」
長政は軽く笑って答えた。
「なあに、源左衛門。人間なんて、どこで生まれようが同じことよ。ちったあ言葉が違うくれえで、そんなに怖がることあるめえ」
「だけんどよ、ここじゃあおいらら外国人じゃねえか。どうやって暮らしていくんだい?」
「そりゃあ、やってみにゃあわかるめえ。とにかく、まずは腹ごしらえだ。この暑さじゃあ、喉も乾くってもんよ」
二人は港を離れ、にぎやかな市場へと足を向けた。屋台が立ち並び、見たこともない料理の香りが漂う。長政は物怖じせず、一軒の屋台に近づいた。
「おっちゃん、うめえもんあるかい?」
当然、屋台の主人は首をかしげる。言葉が通じないのだ。長政は身振り手振りを交えて、食べ物が欲しいことを伝えようとした。
「ほら、こうやって食うんだ。うめえもんくれよ」
主人は長政の仕草を見て、やっと理解したようだ。笑顔で何かを差し出してくる。長政はためらうことなく、その得体の知れない料理に噛りついた。
「うっま! これァ、なんちゅう味だ!」
辛さと甘さ、酸味が絶妙に調和した味に、長政は目を見開いた。隣で佐藤はおずおずと口に運ぶ。
「うっ、辛え! 水、水くれ!」
長政は大笑いしながら、屋台の主人に水を頼んだ。
「お前さんも、もうちっと度胸つけねえとな。こんなうめえもん、食わずに帰るなんてもったいねえぜ」
その日から、長政のアユタヤでの生活が始まった。彼は持ち前の好奇心と度胸で、次々と新しいことに挑戦していった。
第二章:バンコクとの出会い (第2部)
ある日、長政は市場で武器を売る店を見つけた。日本刀とは異なる形状の刀剣に、彼は興味を示した。
「へえ、こりゃあ面白れえな。ちったあ振らせてもらおうかな」
店主は長政の様子を見て、刀を手渡した。長政は慣れた手つきで刀を構え、素振りを始める。その動きは流れるように滑らかで、見る者を魅了した。
周囲の人々が集まってきて、長政の姿に注目し始めた。その中に、一人の武人らしき男がいた。彼は長政に近づき、流暢なポルトガル語で話しかけた。
「お前、剣の腕前はなかなかだな」
長政は言葉こそ理解できなかったが、相手の態度から褒められていることは分かった。彼もポルトガル語で返そうとしたが、うまく言葉が出てこない。
「あー、そりゃどうも。おいらァ、ちったあ刀を振るのが好きでね」
武人は長政の言葉を理解できなかったが、その態度に興味を示した。通訳を呼び寄せ、会話を続けようとする。
通訳が到着し、二人の会話が始まった。
武人:「お前の名は何という?」
長政:「おいらァ山田長政って言うんだ。あんたは?」
武人:「私はオーヤ・センムアン、王の近衛兵の隊長だ。お前の剣の腕に興味がある。わが隊で腕前を試してみないか?」
長政:「へえ、そいつァ面白そうだ。やらせてもらおうじゃねえか」
こうして長政は、思いがけず王宮への道を開くことになった。彼の剣術の腕前は、オーヤ・センムアンを驚かせるに十分だった。
王宮での試合の日、長政は緊張することなく、むしろ楽しんでいるように見えた。
「よっしゃ、かかってこい!」
長政の剣さばきは、シャムの武人たちを驚かせた。彼の動きは予測不可能で、しかも効率的だった。あっという間に、何人もの相手を倒してしまう。
オーヤ・センムアンは感心した様子で長政に近づいた。
「見事だ、山田。お前の腕は本物だ。わが隊に加わる気はないか?」
長政は、通訳を通してその申し出を聞いた。彼は少し考え込んだ後、にやりと笑って答えた。
「いいねえ、やらせてもらうよ。だけどよ、おいらにも条件がある」
「何だ?」
「おいらァ、いろんなことを学びてえんだ。剣だけじゃなく、ここの言葉も、政治のことも、なんでもだ。そいつを許してくれるんなら、喜んで力を貸すぜ」
オーヤ・センムアンは長政の要求を聞いて、少し驚いたような表情を浮かべた。しかし、すぐに納得したように頷いた。
「分かった。お前の望み通りにしよう。だが、その代わりに全身全霊でわが隊に仕えることを誓え」
「あいよ。そりゃあ、当然のことよ」
こうして長政は、シャム王国の近衛兵として仕えることになった。彼の日々は、剣の稽古だけでなく、言語の習得、政治制度の学習、そして現地の文化や習慣の理解に費やされた。
第二章:バンコクとの出会い (第3部)
ある日、長政は王宮の図書館で、熱心に書物を読みふけっていた。そこへ、同じく近衛兵の一人であるソムチャイがやってきた。
「おい、長政。またここで勉強かい? お前ってば、本当に止まることを知らねえな」
長政は顔を上げて、にっこりと笑った。
「なあに、こんなのは序の口よ。まだまだ知らねえことだらけさ。お前こそ、ちったあ本でも読んだらどうだい?」
「冗談じゃねえ。俺ァ剣を振るうのが仕事だ。お前みてえに、頭でっかちになりたくねえよ」
「そいつァ違うぜ、ソムチャイ。頭と腕、両方使えてこそ一人前ってもんよ。それに、知れば知るほど面白えもんなんだ」
ソムチャイは首を傾げた。
「お前の言うことは、いつも難しくてよく分かんねえよ。でもまあ、お前のおかげで俺らの仕事がやりやすくなってるのは確かだな」
長政の知識欲は、彼を単なる武人以上の存在に押し上げていった。彼は言語を習得し、現地の文化を理解し、そして政治の仕組みまでも把握していった。その知識は、彼の立場を徐々に向上させていった。
しかし、すべてが順調だったわけではない。長政の出世は、一部の保守派の反感を買うことにもなった。
ある日、長政は宮廷での会議に出席していた。そこで、ある大臣が彼に向かって非難の言葉を投げかけた。
「山田長政、お前のような外国人が、どうして我が国の政に口出しする権利があると思うのだ?」
長政は、その言葉に動じることなく答えた。
「なあに、大臣殿。おいらァただ、この国のためになることを言っているだけさ。外国人だろうが何だろうが、いい考えは採用すりゃあいいじゃねえか」
「無礼者! お前のような者に、我が国の伝統が理解できるはずがない」
長政は冷静に答えた。
「伝統ァ大事だ。だがよ、時代に合わせて変わっていかなきゃあ、国は滅びちまう。おいらァ、ただそれを言ってるだけよ」
この発言は、会議場に衝撃を与えた。多くの者が長政の大胆さに驚いたが、一方で彼の言葉に頷く者もいた。
長政の考え方は、時に物議を醸すこともあったが、それ以上に多くの支持者を集めていった。彼の柔軟な思考と行動力は、硬直化しつつあったシャムの宮廷に新しい風を吹き込んだのだ。
そんな長政のもとに、ある日、日本から来たばかりの若い武士が訪ねてきた。
「山田殿、私は田中五郎と申します。日本を発って間もない身でございますが、ぜひともお目通りを願いたく…」
長政は温かく彼を迎え入れた。
「よく来たな、田中。あんたみてえな若えもんが来てくれて、おいらァ嬉しいぜ。ここでの暮らしはどうだい?」
「はい…まだ慣れませぬ。言葉も通じず、食べ物も口に合わず…」
長政は優しく笑って、田中の肩を叩いた。
「そりゃあ、誰でも最初はそうさ。だが、心配すんな。あんたも、すぐに慣れる。それに、ここにゃあ面白えことがいっぱいあるんだ」
「面白いこと、ですか?」
「ああ、そうさ。新しい言葉を覚えるのも、見たこともねえ料理を食うのも、みんな楽しみってもんよ。それに、ここの連中と付き合ってりゃあ、いろんなことが学べる。おいらァ、毎日が発見の連続で、退屈する暇なんてねえくらいさ」
田中は長政の言葉に、少し元気づいたように見えた。
「山田殿のように、私もこの地に慣れることができるでしょうか…」
「当たり前さ。あんたも、おいらと同じ日本人じゃねえか。根性があるはずだ。さあ、今日から一緒に頑張ろうぜ。おいらが、あんたの面倒を見てやる」
こうして長政は、新たな仲間を得た。彼の周りには、次第に彼を慕う者たちが集まってきた。日本人だけでなく、シャムの人々も、そして他の国からやってきた者たちも、長政の魅力に惹かれていった。
長政の日々は、常に新しい挑戦に満ちていた。彼は武芸を磨き、政治に参加し、商売にも手を染めた。そのどれもが、彼にとっては刺激的な経験だった。
「なあに、人生なんて、やってみにゃあわからねえもんさ。失敗したっていいじゃねえか。そこから学べばいい」
長政のこの言葉は、多くの人々の心に響いた。彼の前向きな姿勢と果敢な挑戦は、周囲の人々を勇気づけ、彼らもまた新しいことに挑戦するようになっていった。
長政は満面の笑みを浮かべながら、新たな朝を迎える準備をした。彼の冒険は、まだまだ続いていくのだった。