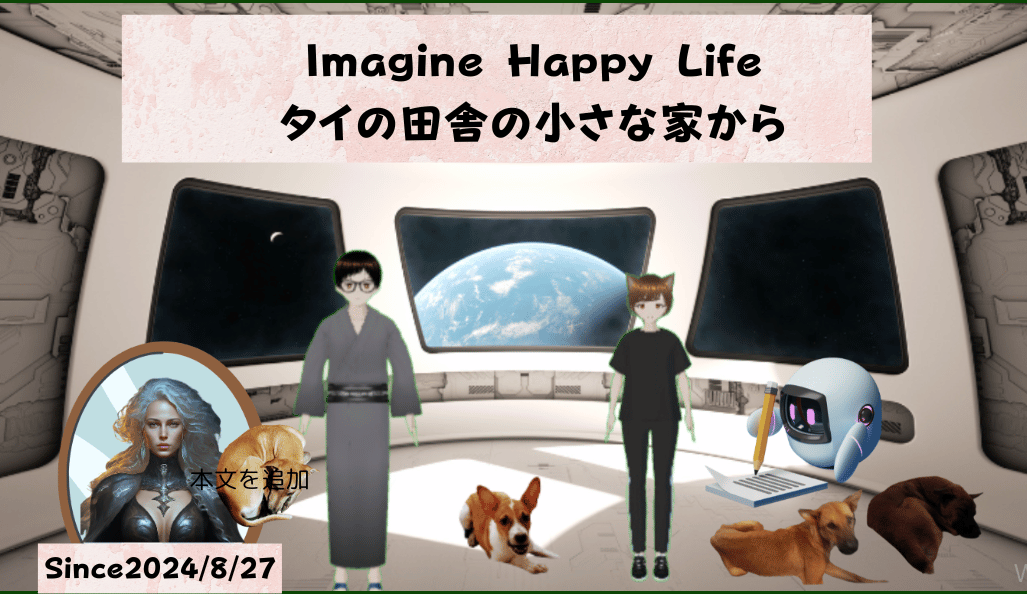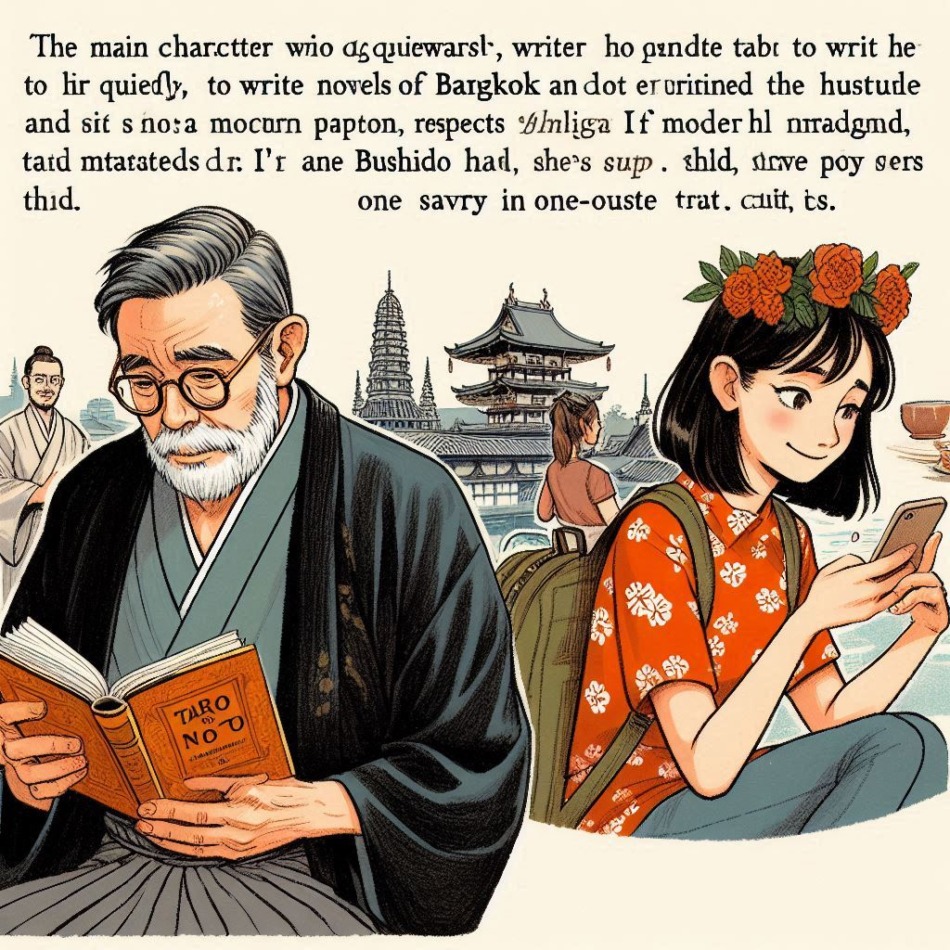画像提供:Being
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場所、事件等は著者の想像によるものです。実在のものとは一切関連がなく、また、実際の出来事に基づくものではありません。
バンコク怪奇譚1 『バンコクの呪われた扇風機』

画像提供:Being
大田太郎の心象風景は、バンコクの喧噪を背に、新たな住居への期待と不安が交錯するものでした。新しい部屋の窓から差し込む朝日を想像するとき、彼の心は不思議なざわめきに包まれます。横綱不動産という名の小さな会社を率いる彼は、タイ人スタッフと共に、タイの文化と日本人の気質を繋ぐ橋渡しをしていました。
彼の選んだ住まい、それは地元民向けの古く質素なアパートであり、月々の家賃はたったの3000バーツ。日本人には想像もつかないような環境でしたが、太郎にとってはビジネスの戦略上、必要な選択だったのです。そしてある日、彼の日常は突如として変貌を遂げます。アパートの住人からの騒音クレームがきっかけでした。太郎の日課である相撲の四股が原因でした。
引越し先を探し求める中、タイ人従業員のレックが、運河沿いのコンクリート造りのアパートを紹介します。最上階に位置する部屋は、中国系のタイ人が住んでいた形跡があり、扇風機からは不吉な気配を感じずにはいられませんでした。
読み上げ

画像提供:Being
新しいアパートに越してきた日、太郎はポンおばさんと出会います。彼女は若いころ日本にいたことがあり、カタコトの日本語で警告します。「その扇風機、寝るときは使うな、危ない」。しかし太郎はその警告を軽んじます。
その夜、不気味な夢にうなされた太郎。夢の中で、一組のタイ人が激しく言い争い、女が扇風機で男を殴りつける光景がありました。太郎が目覚めたとき、部屋は静まり返っていましたが、心の奥底には不穏なざわめきが残っていました。
そして翌朝、太郎はいつものようにシャワーを浴び、四股を踏んだ後、急いで出勤しようと階段を駆け下ります。しかし、ポンおばさんの警告が現実のものとなり、階段で滑って転落死してしまいます。彼の手には、バナナの皮。そして数日後、扇風機はアパートのゴミ捨て場に捨てられていました。それはただの扇風機ではなかったのです。

画像提供:Being
アパートのゴミ捨て場に、謎の文字が刻まれた古い扇風機が捨てられた数日後、新たなる章が静かに幕を開ける。アメリカからやってきたバックパッカー、ジョンは、旅の途中で耳にしたバンコクの古びたアパートの噂に興味を引かれ、その門を叩いたのだった。
ジョンは冒険心旺盛で、世界を旅しながら東南アジアの神秘に魅了されていた。ポンおばさんから部屋の鍵を受け取り、太郎の悲しい運命について耳にする。おばさんはジョンにも忠告する。「夜、その扇風機を使うな。不吉なことが起こるかもしれんぞ」と。しかしジョンはこの忠告を単なる迷信として受け流し、心配することなく部屋に足を踏み入れた。
部屋には、ゴミ捨て場から持ち帰った扇風機が置かれており、ジョンは疑いもなくそれをコンセントに差し、スイッチを入れた。扇風機はゆっくりと首を振り始め、古びた風がジョンの部屋に流れ込む。
夜が深まるにつれて、ジョンはバンコクの蒸し暑さを忘れるかのように、扇風機をつけたまま眠りに落ちた。だが夜中、部屋には不可解な囁き声がこだまする。半覚醒の状態で囁きの声に耳を傾けると、それは扇風機から発せられているかのようだった。「逃げて…」その言葉が何度も繰り返されるが、やがて「来て…」という誘いへと変わる。
翌朝、ジョンは前夜の出来事を何も覚えていなかった。目を覚ますと、彼の部屋の壁には奇妙な記号が描かれており、その中央には扇風機が静かに佇んでいた。ポンおばさんは、ジョンが姿を見せないことに不安を感じ、扉を叩くが、中からは返事がない。ただ扇風機からは、依然として不気味な囁き声が漏れ聞こえていたのだった。
ジョンの物語は、このアパートの新たな伝説の一部となり、タイの地で語り継がれるだろう。物語はここで一つの結末を迎えるが、それはまた別の物語の始まりでもあるのである。

【新パヤナーク戦記】