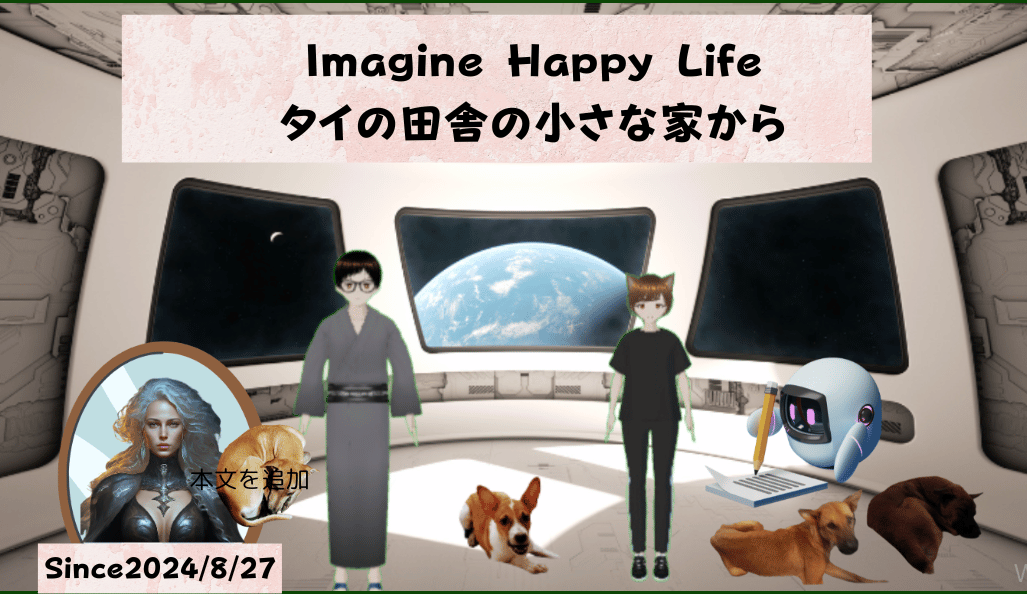画像提供:Being
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場所、事件等は著者の想像によるものです。実在のものとは一切関連がなく、また、実際の出来事に基づくものではありません。
異境の囁き―バンコク怪奇譚1 『バンコクの呪われた扇風機』
バンコク怪奇譚2 『恐怖の虫喰い寺院』
異境の囁き―バンコク怪奇譚3 バンコクの黒犬伝説 – 恐怖の深夜タクシー
バンコク怪奇譚2 『恐怖の虫喰い寺院』

画像提供:Being
バンコクの都心部の喧騒を抜け、都市の喧騒とは対照的な郊外へと足を伸ばすと、観光客の目にはつかないような、ひっそりと静まり返った小さな寺が佇んでいた。この地は、昆虫食研究者である桜井桃子と彼女の友人ブンにとって、未開の地であり、未知の昆虫食の研究を進める秘境だった。
「ねえ桃子、あれ見て!なんて大きなカブトムシ!」ブンが指さした先には、デザインが風変わりな扇風機が回り、その周りを珍しい種類のカブトムシが飛び交っていた。
筋肉質な腕を組みながら、桃子はうなずいた。「確かに珍しいカブトムシだけど…でも、何かが変だね。こんな場所で、こんな大きなカブトムシがなぜ?」
二人は好奇心を刺激され、珍しいカブトムシを追いかけるうちに、気がつけば静まり返った廃寺の中にいた。ブンは無我夢中でカブトムシを追いかけ捕まえたが、一方の桃子は不安そうに眉をひそめていた。
「ブン、食べるのはやめたほうが…」桃子が警告するが、ブンは興奮して口にした。
「大丈夫よ、昆虫食はタイでは普通のことだもの。」ブンは自信満々に答え、捕まえたカブトムシを口に放り込む。
しかし、その後すぐにブンの様子がおかしくなった。彼女は意味不明な言葉をつぶやき、目には狂気が宿る。
「ブン、大丈夫?何言ってるの?」桃子が心配し声をかけるも、ブンは答えず、不規則に動き始めた。
「桃子、逃げて…私、何かが…うわあああ!」ブンの叫び声が寺全体を震わせる。

画像提供:Being
恐怖に駆られた桃子は、廃寺の奥へと逃げ込むが、そこは地下室に続く不気味な空間だった。壁を這う無数のカブトムシ。そして、追いすがるブン。
「ブン、これ以上は…来ないで!」桃子は後ずさりながら叫ぶ。
「桃子…助けて…」ブンの声はもはや人間のものではなくなりつつあった。
絶体絶命の中、桃子は祖母が唱えていた南無妙法蓮華経を思い出し、必死に唱え続けた。

画像提供:Being
目が覚めた桃子は大学のキャンパスにいた。ブンが笑顔でカブトムシ料理を差し出している。
「南無妙法蓮華経ってなに?」ブンが無邪気に尋ねる。
桃子はただ、深く息を吸い込むと、この平穏な日常が真実であることを願いながら、答えた。
「それはね、おばあちゃんがいつも唱えてるお経のこと。困ったときに助けてくれる魔法の言葉みたいなものだよ。」桃子はブンの瞳を見つめながら、ほっとしたように微笑んだ。
ブンは首をかしげながらも、桃子の言葉に安心したように笑いかけた。「へぇ、すごいね。桃子には魔法があるんだね。」
「うん、でもね、本当は…」桃子の声は小さくなり、彼女は遠い目をした。「本当は、自分を守るのは自分の強さなんだと、おばあちゃんも言ってたよ。」
その時、ブンの手からカブトムシ料理がこぼれ落ちた。桃子は思わずそれを拾い上げるが、その瞬間、彼女の脳裏には廃寺の光景が鮮明に蘇った。
「実はね、あのカブトムシ…私たちが廃寺で見たのと同じような…」ブンが言葉を切らすと、桃子はゆっくりと頷いた。
「あれは、ただの幻じゃなかったのかもしれないね。でも、今はここにいる。大切なのは、今を生きることだよ。」桃子はブンの手を握り、力強く言った。
ブンは桃子の手を握り返し、二人は互いに笑い合った。しかし、その笑顔の裏では、あの恐怖の記憶がまだ鮮やかに残っていた。それは、二人だけの秘密として、心の奥底にしまわれた。
日常に戻ったように見えたタイの大学キャンパスだが、二人にとってはもはや以前のような単純な場所ではなかった。バンコクの郊外にある廃寺での出来事は、桃子とブンに大きな変化をもたらしたのだった。
昆虫食の研究は続けられるが、今後はより慎重に、そして神秘的な力を尊重しながら進められることになるだろう。そして、その研究が彼女たちに何をもたらすのか、それは誰にも予測できない未来のことであった。

【新パヤナーク戦記】